どんな農業をしていますか?

鴨方町の水田
平成元年には、個人名義の水田30a(3~4枚)を使用して、山田錦(酒米)の栽培を開始しました。その後、徐々に鴨方町で、個人名義の借地を増やしていきましたが、中山間地域で区画も小さいことからあまり効率がよいものではありませんでした。
転機が訪れたのは、平成15年の「酒米栽培振興特区」の認定でした。鴨方町が、地権者から水田を借りて、丸本酒造に貸し付ける方式が取られたのです。個人名義だった農地も含めて、約3haを丸本酒造が耕作することになりました。それでも30枚以上に別れ、農業機械が自走で移動できないほどには点在したものでした。
しかし、地道に耕作を続けてきた結果、近隣の矢掛町からの水田を借りられるようになります。平成21年の農地法改正以降は、解除条件付貸借の方式に移行しましたが、現在16haの水田を耕作するまでになったのです。矢掛町の水田は、30a~1ha区画で、3カ所程度にまとまっているため、作業効率があがりました。水路の溝掃除や草刈りなどの共同作業は地権者にお任せし、高いところで1万円の賃借料を払っています。
丸本酒造の社員は、22人いますが、田植え、稲刈は総出で行い、他の管理作業(肥培管理、除草など)は、営農部長1人を含む2~3人でまわしています。栽培技術の習得には試行錯誤があって5年ほどかかりました。大きな誤りに気づいたのは、国税庁に勤務し、酒の専門家であった永谷正治先生との出会いのおかげでもありました。
多肥で多収の米はタンパク質を多量に含んでいますが、酒造ではこのタンパク質を削ることになります。すなわち等級は高くとも、このような米はよい酒米ではないということなのです。
こうして、永谷先生の三黄(さんおう)の稲づくり(定植前、出穂前、収穫前の窒素の施肥を抑制する)を取り入れていくことになりました。山田錦は原種に近いため、窒素過剰に弱く、この栽培方法に適しています。


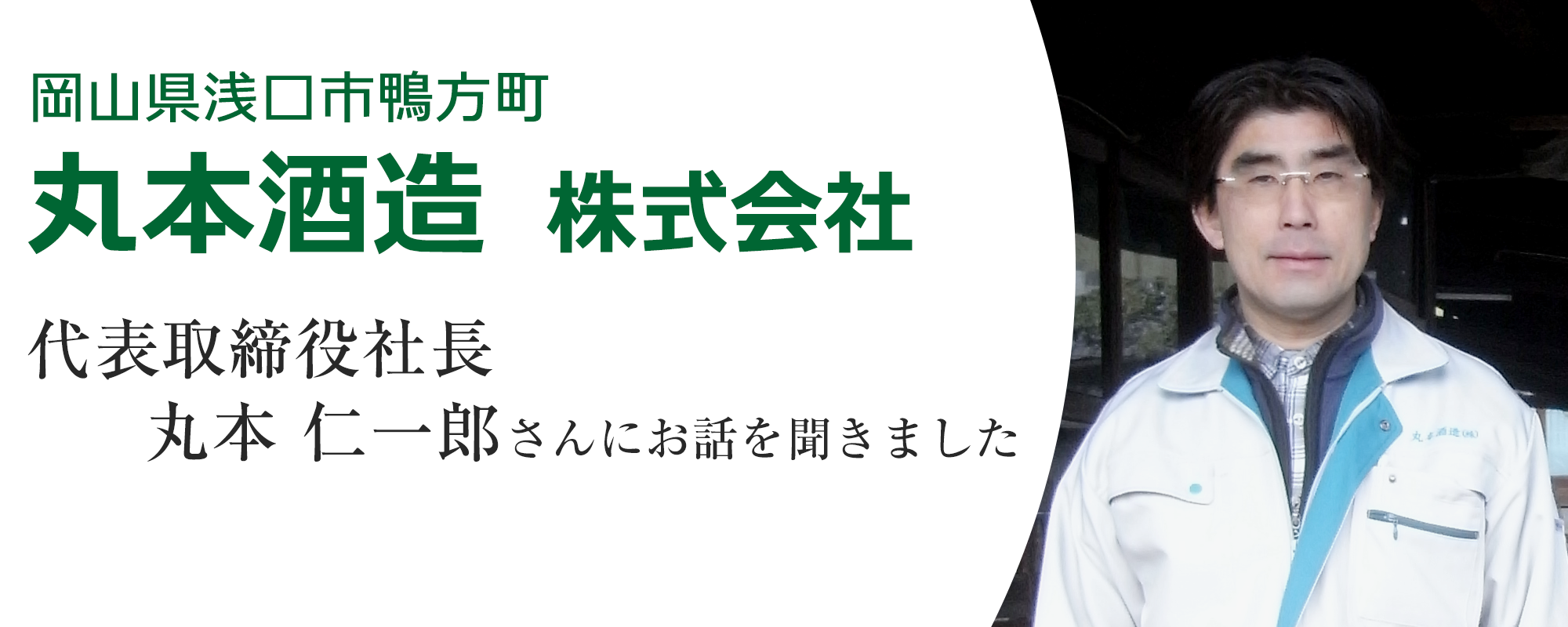
 昔の佇まいを残す丸本酒造の建物
昔の佇まいを残す丸本酒造の建物 鴨方町の水田
鴨方町の水田 有機JASの認定を取得した水田
有機JASの認定を取得した水田