農地を活かし担い手を応援する 利用状況調査にタブレット導入 熊本・玉東町農業委員会
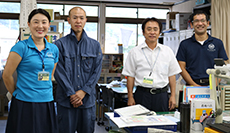

昨年、新体制に移行した熊本県の玉東町農業委員会(山野信也会長)。農地の現状を把握・整理しながら担い手へつなぐために、また、農業経営の源である農地を守るために、農地利用最適化推進委員11人と農業委員11人、そして事務局職員の全員が一丸となり活動している。
同農業委員会は、新体制に移行してから2回目となる利用状況調査を、7月末から9月末までの2カ月間、GPS(衛星利用測位システム)を活用したタブレットを用いて行っている。推進委員が事前に調査した耕作放棄地と思われる農地と農業委員の情報、そして調査中に新たに発見した耕作放棄地を担当地区の推進委員と農業委員に事務局職員が同行し11地区を見回る。
タブレットは全筆調査を効率的に行うために、2015年に導入した。導入前は出力した地図を手に、現地を確認しながらホワイトボードに必要事項を記入して写真を撮影していた。そのため、山林や荒地の中に混在する田畑では目視の確認が正確さに欠ける時もあった。現在は、事前にタブレットへ現地情報を入力することにより、地図やリストの作成が不要となった。GPSの機能の位置情報をもとに、紙の地図では分かりづらかった筆界の確定ができ、正確な位置での調査が可能になり、間違いが激減した。
確認作業と併せて、分類の確定や記入を同時に行うことができ、タブレットの画面を用いることで、確認写真に用いていたボードへの記入作業が不要となった。結果、導入前には1日当たり30〜40筆だった利用状況調査の作業が、60〜100筆と、ほぼ倍に作業効率が上がった。
山野会長(60)は「タブレットを導入したことで、手持ちの資料がなくとも正確な調査が効率的に行える。委員の参加日数もほぼ半分になった。簡素化ができ便利なタブレットは、利用状況調査を進める委員にとって非常にありがたいものだ」と話す。
同農業委員会では、農地集積の具体的な取り組みとして、地域との合意形成を図るために、推進委員と農業委員が中心となり、地域の話し合いに参画する方向で計画を立てている。また、遊休農地対策や耕作放棄地解消については、3地区で実践チームを編成して目標を設定している。
山野会長は「農家の後継者が少ない中、農業委員会としてどのような策をとるべきか模索中だ」と話し、担い手育成で後継者を育てながら並行して農地集約に向けた活動を行うことが最良だと考える。「後継者や担い手がいれば、耕作放棄地も解消され、農地の集約にも拍車が掛かるはずだ」と力強く語った。
町では昨年、町外からの新規就農者が2人生まれた。同農業委員会は、今後も農業委員と推進委員が連携しながら新規就農希望者に農地をあっせんするなど、地域の担い手への農地集積や集約化に向け活動していく。
写真上=玉東町農業委員会事務局の皆さん。左から木下衣美主査、高瀬伸一主幹、古閑康広事務局長、井上克弘局長補佐
写真下=農業委員と推進委員、事務局職員が三位一体で農地の利用状況を確認する
