中山間地域 農業委員会の挑戦(9) 鳥獣害対策の発信に注力 京都・舞鶴市農業委員会

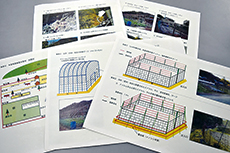
中山間農業と切っても切れないのが鳥獣害対策だ。被害に遭うと生産意欲はそがれ、農地の荒廃につながる恐れがある。この中山間部ならではの地域課題に対抗するため、京都府舞鶴市農業委員会(谷口和会長)では特別委員会の一つとして「有害鳥獣対策委員会」を設置している。
同市ではさまざまな鳥獣が猛威を振るい、2017年度の農作物被害額は出荷用と自家用合わせ約2千万円に及ぶ。「被害のせいで耕作をやめてしまう高齢農家は多いが、諦めてはいけない」と、対策委員会の櫻井昭秀委員長(72)は声を大にする。
対策委員会は計5人の農業委員、農地利用最適化推進委員が主要メンバーとして参加し、市内農家への情報発信を活動の柱とする。昨年4月には市内全集落の「農事組合」の組合長に手作りの対策事例集を配布した。櫻井委員長をはじめ委員ら自身の対策を中心にまとめ、写真や図で分かりやすく紹介した。
例えば櫻井委員長は自宅ごと隣接する圃場を電気柵で囲う他、知り合いの猟師から譲り受けた猟犬による追い払いと自作のししおどしを組み合わせている。ししおどしは裏山から獣が近づくとセンサーが反応し、ライトが点灯してラジオを大音量で流す仕組み。「猟犬の効果も大きかった」(櫻井委員長)。以前はイノシシやシカ、サルの被害でお手上げだったが、対策を始めてからは激減し、ここ10年ほど被害はゼロだという。
他にも、農地の巡回中に見つけた農家のアイデアも掲載。電気柵とワイヤメッシュ柵の二重張りで多種の動物に備える例やパイプハウスの骨組みを活用した防護柵などの例が集まった。農家がまねできそうな創意工夫が光る事例に絞っているのが特徴だ。
対策委員会では、農業委員や推進委員の活動を通じて地域と密につながれる農業委員会の強みを生かし、現場の優良事例の収集と発信に力を注いできた。2016年度には、当時の対策委員会のメンバーが地元農家への聞き取り調査を重ね、それを基に研修会を開催。市内農家およそ180人を集めた。
今後は農家全戸まできめ細かく情報提供できるよう、農業委員会だよりと抱き合わせて事例集を配布する方法なども検討している。農業委員会事務局は「事例紹介に終わらず、動物ごとの防除のポイントのような基礎知識なども充実させていきたい」と話す。
写真上=櫻井委員長
写真下=対策事例集では写真や図をふんだんに活用
