農地を活かし担い手を応援する 積極的に現場で働く農委会へ 島根 松江市農業委員会

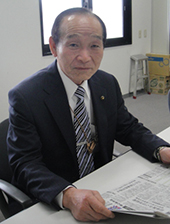
山陰のほぼ中央に位置する島根県松江市。大橋川・宍道湖・中海に沿って沖積平野が広がり、都市近郊型園芸、稲作、また、干拓地では露地野菜の栽培が盛んに行われている。現在、松江市農業委員会(原保雄会長、農業委員37人)では、2017年7月からの新体制へ円滑に移行できるよう、農地利用の最適化に係る年間活動計画や活動マニュアルの作成に取り組んでいる。
昨年以降、総会では毎回、新体制に関して活発な議論を展開しており、全委員が「より一層現場で動く農業委員会にならなければいけない」と強く認識している。
松江市は都市近郊農地、平たん部の農地、中山間地の農地が混在し、担い手の状況や経営規模がそれぞれの地域で異なる。そのため、実際の現場活動にあたっては、それぞれの実態に合わせた効率・効果的な活動を展開するための計画やマニュアルが必要となっている。
こうした状況を踏まえ、2016年3月に設置した農業委員会改革調査研究部会において、(1)全体の活動方針(2)地区ごとの活動体制(農業委員と推進委員のチーム構成など)(3)地区ごとの年間活動計画・活動マニュアルについて、調査・研究を進めている。
2016年度は、農業委員、農地中間管理機構の農地集積推進員、松江地域農業再生協議会(市、JAなどで構成する組織)で班を編成し、貸出希望農地の現状確認や、借り手候補者を訪問して意向を伺うなど、現場でのマッチング活動を積極的に実施した。主な対象農地は、15年に調査を行った貸出希望農地のうち、貸し借りの調整がつかなかった農地。この活動により、対象の約4割が新規集積につながったほか、改めて対象農地の状況や課題が認識できた。また、農業委員の現場活動への意識がより高まる結果となった。
原会長は「前年度(2016年度)に現場活動から得られた情報や経験を生かし、全委員が高いモチベーションを持って活動していくための環境を整えていきたい。そのためにも優先事項を定めた活動計画と、分かりやすいマニュアルの作成は必須。農家の声を大切に、現場で得た情報を最大限生かす仕組み・フロー(手順)を構築した上で、とにかく現場で汗をかく農業委員会を目指していきたい」と力強く語った。
写真上=現地確認をする農業委員
写真下=松江市農業委員会の原会長
